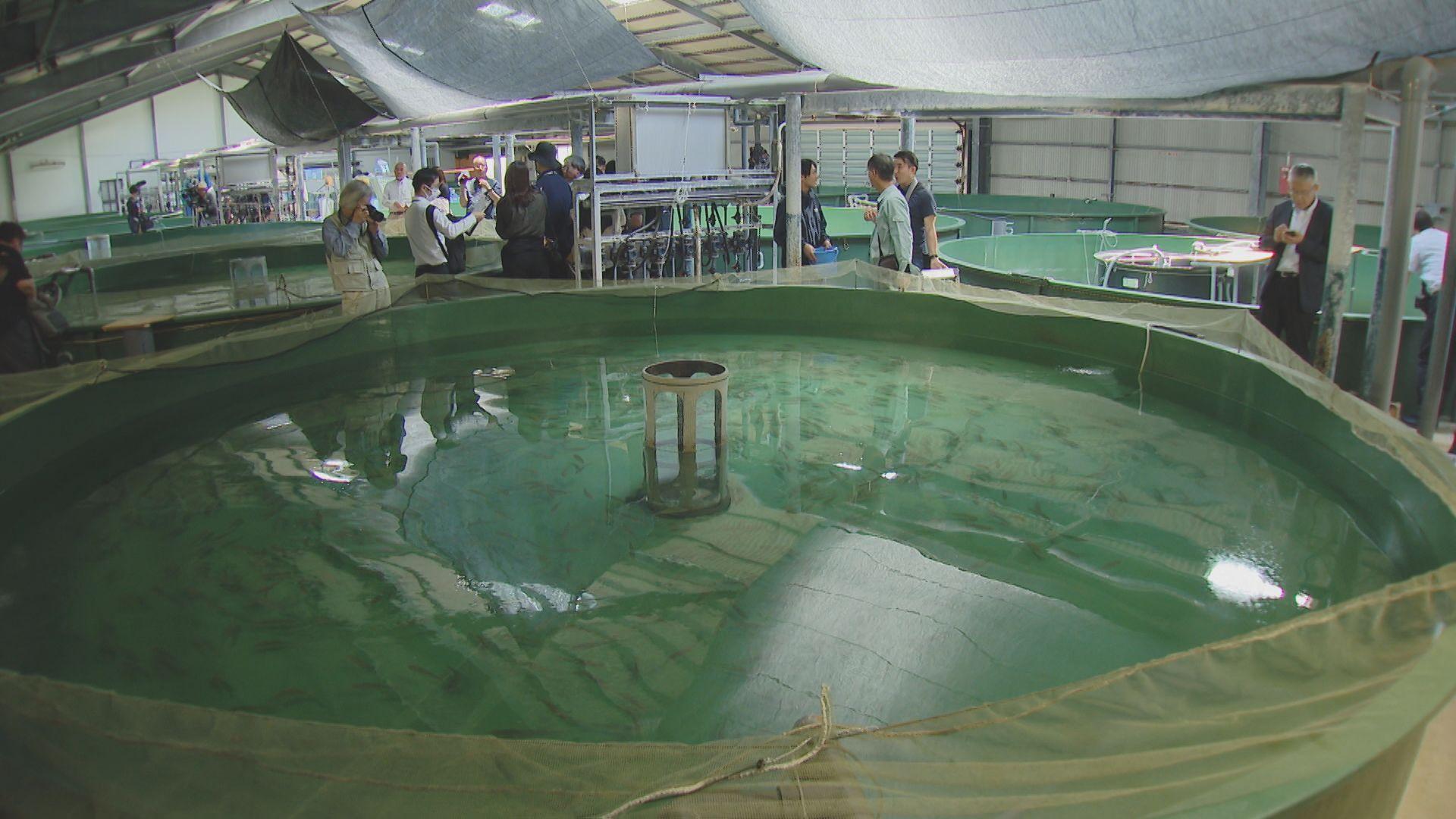最も危険な病原体を扱う長崎大学「BSL-4施設」 厚労省の指定受け、地域住民らに説明
長崎大学の「BSL-4施設」で最も危険度の高い病原体を扱えるよう国が指定したことを受け、大学側は地域住民に対する説明会を開き、今後の方針や対策などについて話しました。
長崎大学坂本キャンパスに建設された「BSL-4施設」について厚労省は24日、エボラウイルスなど最も危険度の高い病原体を扱える施設として指定しました。感染症の予防法や治療法を開発するために研究できる国内初の施設となります。
指定を受け、大学側は地域住民に対する説明会を開きました。
長崎大学高度感染症研究センター・森内浩幸センター長:
「今般、国の重大な決定を受け指定を頂きましたことは長崎大学として大変な栄誉と受け止めています。しかしそれ以上に指定を受けた大学の責任の重さを痛感しているところであります」
「BSL-4」の本格稼働に向けて危険度の高いウイルスの輸入や国内移送には、別途、厚労大臣の指定や承認が必要となります。
森内センター長は、本格稼働までは「年単位になると思う」とした上で「いつを目指してとは、はっきり言えない」と話しました。
本格稼働に向けて大学では現在、危険度の低いウイルスを使った研究と訓練を行っていて、半年に1回、国の査察を受けることになっています。
住民側からは「厳しく監視することを約束してほしい」「住民に真摯に向き合ってほしい」などの声が上がり、安全対策や監視態勢の維持・強化、住民への情報開示を求めました。
山里中央自治会・道津靖子会長:
「自分たちの生活圏内に(危険度の高いウイルスが)入ってくることに不安はあると思う。でもその不安を払拭してくれるのは大学のきちんとした管理と安全対策をやっていくという姿勢だと思いますのでそれを住民に示してほしい」
大学側は「地域の目でも監視してもらい、ヒューマンエラーがないように幾重にも対策を講じたい」としています。